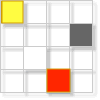

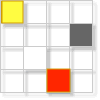
|

|
|
|
第94回 |
2025年3月22日
「ESD の展開についての一考察─ドイツの成人教育からみるベルリン宣言の意義─」 佐野敦子
「障害のある者の教育を受ける権利」 松村好恵
「ドイツ大学財政制度における評価配分の抑制:NRW州大学自由法の審議過程を事例として」 横山岳紀
|
|---|
|
|
第93回 |
2024年3月16日
前原健二(2023)『現代ドイツの教育改革―学校制度改革と「教育の理念」の社会的正統性』(世織書房)を語る 前原健二(東京学芸大学)…執筆者の立場から
安原陽平(獨協大学)…第1部(教員)に寄せて
井本佳宏(東北大学)…第3部(学校制度)に寄せて
坂野慎二(玉川大学)…全体討議によせて
|
|---|
|
|
第92回 |
2023年7月29日
「ドイツにおける"Reformpädagogik"研究の展開」 安藤和久(広島大学大学院・特任助教)
「ドイツの幼児教育における子どものSelbstständigkeitに関する研究」 大道香織(広島大学大学院・博士後期課程院生)
「世耕弘一のベルリンに於ける足跡」 荒木康彦(近畿大学・名誉教授)
|
|---|
|
|
第91回 |
2023年5月20日
「ドイツの不登校・早期離学について」ギゼラ・シュルツェ(オルデンブルク大学)、ハインリッヒ・リッキング(ライプツィヒ大学)
「高等教育段階の量的拡大と多様性―ドイツの専門大学を中心に―」坂野慎二(玉川大学)
|
|---|
|
|
第90回 |
2022年12月18日
著者と読む『ドイツの学校法制と学校法学』著者:結城忠 企画:辻野けんま(大阪公立大学)、安原陽平(獨協大学)、濱谷佳奈(中央大学)、棟久敬(秋田大学)、布川あゆみ(東京外国語大学)
|
|---|
|
|
第89回 |
2022年5月29日
「教育政策から見たドイツの保育(就学前教育)政策について」 山本利子(京都大学 日本語・日本文化教育センター)
「インクルーシブ教育改革における日独の教育 概念捉え直しの動向」 津田純子(新潟大学名誉教授)
|
|---|
|
|
第88回 |
2022年3月26日
「世耕弘一の独逸留学(1923-1927)とその意義」 荒木康彦(近畿大学名誉教授)
「教育の中央集権制と分権制-スイスの事例から-」 坂野慎二(玉川大学)
|
|---|
|
|
第87回 |
2021年12月4日
「持続可能性の観点から見たドイツの幼児教育」 木戸啓絵(岐阜聖徳学園大学短期大学部)
「ドイツにおけるコンピテンシー志向の通信簿評価の試み」 卜部匡司(広島市立大学)
|
|---|
|
|
第86回 |
2021年7月24日
「ドイツの中途入職教員 −日本との比較も含めて」 前原健二(東京学芸大学)
「ドイツ民主主義教育の理念と実践」 柳澤良明(香川大学)
|
|---|
|
|
第85回 |
2021年5月29日
「ドイツにおける『森と自然を活用した保育・幼児教育』の研修とその特色」 大道香織(広島大学大学院生)
「ナチズム崩壊直後のシュタイナー学校の再建とその推進者たち -1945年設置のマールブルク校を事例として-」 遠藤孝夫(淑徳大学)
|
|---|
|
|
第84回 |
2021年3月13日
「政治教育における論議性 ―政治的中立性のオルタナティブを模索して―」 今泉尚子(早稲田大学大学院生)
「職業教育・専門教育の高度化に関する一考察」 坂野慎二(玉川大学)
|
|---|
| *この間、コロナ禍に伴い1年ちょっと、研究会を休止。 |
|
|
第83回 |
2019年12月7日
「ドイツにおける学力調査・発達調査の動向分析」 立花有希(宇都宮大学)
「ドイツ教科教育におけるコンピテンシー論の受容と展開 ー地理教育の場合」 山本隆太(静岡大学)
|
|---|
|
|
第82回 |
2019年7月27日
「H.ハイトの価値教育(Werterziehung) 批判と代替案 ー価値づけの主観主義に基づく教授構想に着目してー」 平岡秀美(筑波大学大学院生)
「ドイツにおける教育関係職員の養成に関する研究」 坂野慎二(玉川大学)
|
|---|
|
|
第81回 |
2019年5月25日
「『教育への勇気』と教育的教授論――80年代のドイツ学校教育改革における思潮転換(Tendenzwende)に着目して――」牛田伸一(創価大学)
「ドイツの学校ソーシャルワーカー:制度と実態」前原健二(東京学芸大学)
|
|---|
|
|
第80回 |
2019年3月30日
「学校と生活の媒介方法としての多視点的授業(Mehrperspektivischer Unterricht) ―ヨーロッパ・プロジェクト(Europa Projekt)における多視点的・対話的な授業に着目して―」 田中怜(筑波大学大学院生)
「高校生の法的地位と政治的権利 ―日本とドイツー」 結城忠(国立教育政策研究所名誉所員)
|
|---|
|
|
第79回 |
2018年12月1日
「前期中等教育段階ギムナジウムにおける企業実習の実施理念とその実現 ―バーデン=ヴュルテンベルク州におけるBOGYを事例として―」 藤田駿介(筑波大学大学院生)
「就学義務制度の虐待防止機能―日独比較の視点から―」 荒川麻里(白鴎大学)
|
|---|
|
|
第78回 |
2018年7月28日
「インダストリ4.0に対応する職業教育 ―ジェンダー視点からみるデュアル・システムの変化を中心に―」 佐野敦子(国立女性教育会館)
「オーストリアの高等教育研究に関する一考察 ―専門大学成立過程を中心に―」 田中達也(釧路公立大学)
|
|---|
|
|
第77回 |
2018年5月26日
「ドイツの地理教育におけるESDの展開」 阪上弘彬(兵庫教育大学)
「ハンブルクの保育ヴァウチャー」 山本利子(京都大学科目等履修生)
|
|---|
|
|
第76回 |
2018年3月17日
「ナチズムによる人文主義への批判とその周辺」 曽田長人(東洋大学)
「保育園における保育者のイスラームスカーフ事件」 斎藤一久(東京学芸大学)
|
|---|
|
|
第75回 |
2017年11月25日
「現代ドイツ前期中等教育における学校制度改革に関する研究」 栗原麗羅(上智大学大学院生)
「ドイツ大学の歴史的性格」別府昭郎(元明治大学(博士))
|
|---|
|
|
第74回 |
2017年7月29日
「Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde(LER科)導入をめぐる教授学的論争―1996年Zeitschrift für Pädagogik誌上の諸論考を手掛かりに―」 平岡秀美(筑波大学大学院生)
「ドイツにおける貧困・格差と学力をめぐる問題 -進む学校の終日化と問い直される役割分担のあり方-」 布川あゆみ(東京外国語大学)
|
|---|
|
|
第73回 |
2017年5月27日
「ドイツにおけるギムナジウム政策をめぐる言説分析」 前原健二(東京学芸大学)
「ドイツの就学前教育の現状と課題」 坂野慎二(玉川大学)
|
|---|
|
|
第72回 |
2017年3月18日
「ドイツにおける社会教育学の現代的役割に関する研究 −学校の機能的変容に焦点を当てて−」 高谷昌樹(筑波大学大学院)
「学力格差是正に向けたドイツの取り組み −ノルトライン・ヴェストファーレン州の事例に着目して−」 濱谷佳奈(大阪樟蔭女子大学)
|
|---|
|
|
第71回 |
2016年11月26日
「ヴァルドルフ教育における幼児期の『健康な道徳感覚』の涵養」 相賀由美子(筑波大学大学院)
「専門大学を中心とするドイツの高等教育事情」 高谷亜由子(文部科学省)
|
|---|
|
|
第70回 |
2016年7月16日
Bildungsberichte in Deutschland
Prof. Dr. Axel Gehrmann(ドイツ・ドレスデン工科大学教育学部教授) |
|---|
|
|
第69回 |
2016年5月14日
「地理教育におけるシステムコンピテンシー開発にみる成果と課題」 山本隆太(静岡大学研究員)
「スイス憲法における一般教育と職業教育の同価値原則の意義」 荒川麻里(白鷗大学)
|
|---|
|
|
第68回 |
2016年3月19日
「ドイツ語をつうじた「統合」は可能か?―非識字者向け統合コース改訂とその社会背景についての考察―」 佐野敦子(立教大学大学院博士後期課程修了)
「ドイツ・ニーダーザクセン州における現職教員研修改革のその後」 前原健二(東京学芸大学)
|
|---|
|
|
第67回 |
2015年12月19日
「ドイツ児童書運動における児童書批評紙の内容分析―19-20世紀転換期”Jugendschriften-Warte”紙を対象としてー」 吉本篤子(東京大学大学院生)
「ナチズム体制下のヴァルドルフ学校運動」 遠藤孝夫(岩手大学)
|
|---|
|
|
第66回 |
2015年7月18日
「ドイツ前期中等教育の学校制度に関する政策の分析」 栗原麗羅(上智大学大学院生)
「ドイツ・ギムナジウムにおける政治科の授業展開の分析と解釈」 的場正美(東海学園大学)
|
|---|
|
|
第65回 |
2015年5月16日
「結城忠『憲法と私学教育』について」 荒川麻里(白鴎大学)、辻野けんま(上越教育大学)
「ドイツにおける親の教育権の法的構造」 結城忠(前・白鴎大学)
*今回は結城忠先生古希・退職記念研究会として開催いたしました。
|
|---|
|
|
第64回 |
2015年3月28日
「DGF-ETiK-Projektにおける諸論文のレヴュー」 牛田伸一(創価大学)
「ドイツにおける教育の多様性と質保証」 坂野慎二(玉川大学)
|
|---|
|
|
第63回 |
2014年11月15日(土)
「近代学校における学校の生活乖離批判とその問題性」 田中怜(筑波大学大学院生)
「ドイツ教師教育改革における教師教育スタンダードの影響」 辻野けんま(上越教育大学)
|
|---|
|
|
第62回 |
2014年7月19日(土)
「公共性とコスモポリタンーーシティズンシップ教育の可能性」 中村美智太郎(静岡大学)
「〈神〉の生起と虚偽の起源――スピノザにおける人間的認識の条件について――」 池田全之(お茶の女子大学)
|
|---|
|
|
第61回 |
2014年5月17日(土)
「ドイツの学校経営事情と学校事務職の役割」 前原健二(東京学芸大学)
「ドイツの多文化主義の方向性 -移民「統合」に関わる成人教育からの分析-」 佐野敦子(立教大学大学院)
|
|---|
|
|
第60回 |
2014年3月29日(土)
「ドイツ連邦共和国における宗教科の法的地位をめぐる現代的動向
―ノルトライン・ヴェストファーレン州における「正規の教科」としてのイスラームの宗教科の導入を中心に―」濱谷佳奈(大阪樟蔭女子大学)
「ドイツにおける「私学の自由」と私学助成の法的構造」結城忠(白鴎大学)
|
|---|
|
|
第59回 |
2013年12月14日(土)
「旧東ドイツ地域における二分岐型中等学校制度の現状と今後の展望」 井本佳宏(上越教育大学)
「ドイツの学力向上政策の動向」 坂野慎二(玉川大学)
|
|---|
|
|
第58回 |
2013年7月27日(土)
「1926年「文学世界」誌の児童文学特集をめぐって:ブロッホのカール・マイ論とベンヤミン」 吉本篤子(東京大学大学院生)
「ドイツ民法典における子どもの自立性への親の配慮の明文化過程 ― 「成年年齢の新規制に関する法律」(1974年)を手掛りに―」 荒川麻里(筑波大学
「ニーダーザクセン州における現職教員研修の『分権化』:現状と課題」 前原健二(東京学芸大学)
「ドイツ政治教育における授業分析:解釈学による分析手順と視点」 的場正美(東海学園大学)
|
|---|
|
|
第57回 |
2013年5月18日(土)
「シェリングにおける「新しい神話」の可能性」 中村美智太郎(一橋大学言語社会研究科特別研究員)
「ドイツの「状況的アプローチ」に基づく幼児全日施設の評価に関する一考察 -INA(Internationale Akademie)研究所の試みを通して-」 相賀由美子(筑波大学大学院)
|
|---|
|
|
第56回 |
2013年3月16日(土)
「ドイツの消費者教育と女性向け移民統合コースの調査について ―ボン大学留学報告―」 佐野敦子(立教大学大学院生)
「絶対者の顕現と無限の生成 ―絶対的同一性の理解をめぐるシェリングとシュレーゲルの差異について―」 池田全之(お茶の水女子大学)
|
|---|
|
|
第55回 |
2012年11月24日(土)
「オーストリア・ウィーンにおける学校制度改革と学力向上策」 田中達也(川口短期大学)
「ドイツの高等教育における質保証の動向について」 高谷亜由子(文部科学省)
|
|---|
|
|
第54回 |
2012年7月28日(土)
「シュタイナー思想における「想像力」の「発達」 ―倫理的個人への「発達」を導く「新しい神話」としての人智学―」 河野桃子(東京大学大学院生)
「ヴァルドルフ教員養成の「等価性」認定と教員養成の国家独占の否定 -連邦行政裁判所判決(1993年)を中心にして-」 遠藤孝夫(岩手大学)
「過去と向き合うドイツー反ナチ抵抗運動から記憶文化へー」 對馬達雄(秋田大学名誉教授)
「ドイツ教育政策の立案とその評価」 坂野慎二(玉川大学)
|
|---|
|
|
第53回 |
2012年5月19日(土)
「公立学校教員の憲法上の権利と職務命令 -ドイツにおける原子力反対バッジ裁判を参考として-」 安原陽平(早稲田大学大学院博士後期課程・東京学芸大学非常勤)
「ドイツにおける学校の自律性(Schulautonomie)の法的構造」 結城忠(白鴎大学)
|
|---|
|
|
第52回 |
2012年3月10日(土)
「オランダにおける私学助成制度に関する研究」 澤田 裕之(筑波大学大学院・日本学術振興会特別研究員)
「ドイツの高等教育機関における能力育成-理論と実践の統合の試み-」 坂野慎二(玉川大学) |
|---|
|
|
第51回 |
2011年11月26日(土)
「ドイツの高等教育改革の諸相--高等教育人口の拡大を巡って」 高谷亜由子(文部科学省)
「80年代ドイツ教育改革の参照先としての「教育的教授」論――「教育的教授」論とノルトライン・ヴェストファーレン州85年版学習指導要領の間 」 牛田伸一(創価大学)
|
|---|
|
|
第50回 |
2011年8月27日(土)
「グローバル化と成人教育 ~ドイツの移民教育政策を軸に~」 佐野敦子(立教大学大学院)
「『過去の克服』の尺度はなにか――1950年代西ドイツにおける『過去の克服』の典型としての後期ハイデガーの存在思索」 池田全之(お茶の水女子大学)
|
|---|
|
|
第49回 |
2011年5月21日(土)
「地域共通学校改革の動向:研究ノート」 前原 健二(東京学芸大学)
「ドイツにおける「私学の自由」と私学助成」 結城 忠(白鴎大学) |
|---|
|
|
第48回 |
2010年11月27日(土)
「『帰ってきた、もじゃもじゃペーター』における「しつけ」」 荒川麻里(筑波大学)
「教育報告書にみるドイツの教育改革の検証」 坂野慎二(玉川大学)
|
|---|
|
|
第47回 |
2010年5月22日(土)
「ドイツにおける終日学校政策の展開と課題」 布川あゆみ(一橋大学大学院)
「エルフルトの生活とエルフルト大学の歴史」 別府昭郎(明治大学)
|
|---|
|
|
第46回 |
2010年3月27日
「DDRにおける教育学と「生きられた教育思想」:教師のライフヒストリーを検討する」 木下江美(一橋大学大学院)
「労働的人間形成の論理とそのアクチュアリティについて―意識の自己形成 をめぐる1800年前後のドイツ思想の一断面―」 池田全之(お茶の水女子大学) |
|---|
|
|
第45回 |
2009年11月28日(土)
ドイツにおける道徳教育改革の動き 高谷亜由子(文部科学省)
ドイツ生涯学習における“変容”“ネットワーク”概念について:ドイツ社会教育 施設視察から 三輪建二(お茶の水女子大学) |
|---|
|
|
第44回 |
2009年8月29日(土)
ドイツを中心としたヨーロッパの歴史教育についての一考察 柴田政子(筑波大学)
「移民を背景に持つ」生徒の位置付け ―学力と属性との分析を手がかりに― 山本利子(関西学研医療福祉学院非常勤)
フンボルト大学理念の再検討 金子勉(京都大学)
戦後ドイツにおける宗教教育の復権とナチズム体験 ―ボン基本法の「宗教志向性」関連条項をめぐる議論の分析 遠藤孝夫(岩手大学) 幕府直轄教育機関旧蔵の独逸語書籍と幕末期の独逸学研究 荒木康彦(近畿大学)
現代ドイツの「教育の機会均等」論議の特質 前原健二(東京電機大学)
|
|---|
|
|
第43回 |
2009年5月30日(土)
「近代ドイツにおけるシラーの美的教育思想」 中村美智太郎(一橋大学大学院言語社会研究科博士課程)
「日本の大学導入時におけるドイツの大学・学部概念」 別府昭郎(明治大学)
|
|---|
|
|
第42回 |
2009年3月14日(土)
「ドイツにおける「教師の教育上の自由」論の現状 ― J.ルクスとH.ビスマンによる2つの新たな理論 ―」 辻野けんま(神戸学院大学非常勤講師)
「ドイツにおける教員の労働時間に関する政策に関する研究」 坂野慎二(玉川大学)
|
|---|
|
|
第41回 |
2008年11月29日(土)
「ドイツの総合制大学構想―大学統合プラン(ダーレンドルフ・プラン)の分析を中心に―」 田中達也(大阪市大大学院博士後期課程)
「歴史の破局と〈認識可能性としてのいま〉―ナチズムをめぐるフーコー、アドルノ、ヤスパース、ベンヤミンの思想的対話」 池田全之(お茶の水女子大学)
|
|---|
|
|
第40回 |
2008年7月26日(土)
「テオドール・リットのデモクラシー教育思想における『世代間関係論』の意義」 宮田倫子(お茶の水女子大学大学院)
「ドイツの政治科教科書と安全保障の再定義―ポスト冷戦時代への政治教育の対応―」 寺田佳孝(名古屋大学大学院)
「オーストリアにおける学力向上政策の動向」 伊藤 実歩子(甲南女子大学) 「ドイツにおける校長の職務とニーズ/公共性 - 全日制学校の拡充を事例として-」 柳澤良明(香川大学) 「教師の授業は学習指導要領改訂によってどのように変化したか ― 10年前と現在のある教師の授業事例の分析 ―」 的場正美(名古屋大学) |
|---|
|
|
第39回 |
2008年5月24日(土)
「ドイツの音楽鑑賞教育の意義と実際 ーー<音楽文化への導入>を視点としてーー」 山原麻紀子(東京芸術大学)
「学校批判としての『教育的教授』論 ――教授学的論理を機軸としたヘルバルトの学校批判とその教授学的意味」 牛田伸一(日本大学)
|
|---|
|
|
第38回 |
2008年3月22日(土)
「ギムナジウムの宗教科と実践哲学科のカリキュラムにみる今日的特徴と課題-
ノルトライン・ヴェストファーレン州の事例研究と質問紙調査にもとづいて-」 濱谷 佳奈 (上智大学大学院)
「ドイツの学校の第三者評価」 坂野 慎二 (玉川大学)
|
|---|
|
|
第37回 |
2007年12月22日(土)
「ドイツにおける『機会均等』の教育制度論」 前原 健二(東京電機大学)
「ドイツ教師教育における資質向上策の動向 ―大学・学位制度改革、KMK教員養成のための基準、教員評価制度改革など―」 吉岡 真佐樹(京都府立大学)
|
|---|
|
|
第36回 |
2007年7月28日(土)
「ドイツにおける通信簿の歴史」 卜部 匡司 (広島大学)
「ドイツにおける学校改革構想に関する一考察」 高橋 英児 (山梨大学)
「ドイツにおける学力政策と学校教育の役割変容 ―全日制学校(Ganztagsschule)の拡充をとおして― 柳澤 良明 (香川大学)
「ドイツの学校における『愛国心』を考える ‐社会的・歴史的背景に焦点をあてて」 大野 亜由未 (広島市立大学) 「ドイツの高等教育財政改革」 金子 勉 (京都大学) 「『独逸学事始』の批判的考察」 荒木 康彦 (近畿大学)
|
|---|
|
|
第35回 |
2007年5月12日(土)
「子どもの教育をめぐる学校と家庭の協力的な任務分担関係とは ――ドイツの初等教育段階における終日学校を事例に」 布川 あゆみ(一橋大学大学院)
「ドイツにおける大学文書館」 別府 昭郎(明治大学)
|
|---|
|
|
第34回 |
2007年3月24日(土)
「DDR・東ドイツ地域のロシア語教師のライフヒストリー --- 近代教育における外国語科目の性格を論じる試み---」 木下 江美(一橋大学大学院)
「ドイツの学力政策と質保証」 坂野慎二(玉川大学) |
|---|
|
|
第33回 |
2006年12月16日(土)
「ドイツ連邦制度改革における教育行政の再編」 高谷亜由子(文部科学省)
「EUにおける成人教育者向け大学院の動向 --- TEACHプロジェクトを中心に--- 」 三輪建二(お茶の水女子大学) |
|---|
|
|
第32回 |
2006年7月29日(土)
「学校の教育活動における教師の裁量余地 ---『教師の教育上の自由』の現代的運用をめぐって---」 辻野 けんま(京都府立大学大学院)
「カント『教育学』における『世界市民主義的』教育思想」 藤井 基貴(愛知県立大学・非常勤)
「ドイツ新教育運動期におけるヘルベルト・オットー学校の授業実践に関する再評価」 内藤 由佳子(高田短期大学)
「ドイツの私立大学の挑戦 ---ヴィッテ・ヘァデッケ大学を例として」 荒木 和夫(新日本アーンスト アンド ヤング税理士法人) 「ドイツにおける教育の『クオリティ・マネジメント』」 南部 初世(名古屋大学) |
|---|
|
|
第31回 |
2006年5月27日(土)
「文部官僚フリードリヒ・アルトホーフの初期中等学校改革構想」 安藤 香織 (中央大学大学院)
「ドイツにおける外国人生徒の教育法制」 結城 忠(国立教育政策研究所) |
|---|
|
|
第30回 |
2006年3月25日(土)
「ブランゲの学校における教育不要論の論理 ---「教育的教授」を解体する「教授学的差異」(Didaktische Differenz)---」 牛田 伸一(日本大学)
「PISA以後のドイツにおける学校制度改革の展望」 前原 健二(東京電機大学)
|
|---|
|
|
第29回 |
2005年12月17日(土)
「ドイツ連邦共和国の宗教科と倫理・哲学科における市民性の育成 --- 1990年代以降のノルトライン・ヴェストファーレン州の事例を中心として」 濱谷 佳奈 (上智大学大学院)
「ドイツにおける高等教育の質保証 --- 中等教育との接続関係を中心に」 坂野慎二(国立教育政策研究所)
|
|---|
|
|
第28回 |
2005年7月30日(土)(拡大フォーラム)
「ドイツにおける通信簿記載事項の変容 --- Kopfnotenの再導入をめぐって」 卜部 匡司 (広島大学大学院)
「オーストリアの郷土科および事実教授カリキュラムにおける「図面と地図」単元の歴史的変遷 ---戦間期オーストリアの学校改革からの伝統---」 伊藤 実歩子 (甲南女子大学) 「1990年代以後ドイツの基礎学校カリキュラム改革 --- 合科・総合学習に着目して ---」 原田 信之 (岐阜大学) 「幕末・維新期の日独交渉史管見」 荒木 康彦 (近畿大学) 「ドイツの政治教育 --- 東アジアへの示唆?」 近藤 孝弘 (名古屋大学) 「ドイツにおける青年職業援助の動向 --- ドレスデン、カッセルでの調査から ---」 生田 周二 (奈良教育大学) |
|---|
|
|
第27回 |
2005年5月21日
「テオドール・リットにおける政治と教育の問題」 宮田倫子(お茶の水女子大学大学院)
「ゲッティンゲン大学の近代性」 別府昭郎(明治大学) |
|---|
|
|
第26回 |
2005年3月19日
「帰朝報告:フォルクスホッホシューレ講師の研修事例」 三輪建二(お茶の水女子大学)
「19世紀ドイツの新人文主義におけるギリシャ語とラテン語、ギリシャとローマの関わりについて」 曽田長人(群馬大学非常勤講師)
|
|---|
|
|
第25回 |
2004年 12月19日
「市民参加による都市農地保全運動について --- クラインガルテンを事例に ---」 高雄綾子(東京大学大学院)
「ドイツにおける異文化間教育に関する一考察 --- 地域社会における教育(学習)活動の視点から---」 帆足哲哉(早稲田大学大学院)
「ドイツの学校法制と学校法学(2)」 結城 忠(国立教育政策研究所) |
|---|
|
|
第24回 |
2004年7月31日(拡大フォーラム)
「カント『教育学』における学校教育論」 藤井 基貴 (名古屋大学大学院) 「ドイツにおける大学教育学構想」 津田 純子 (新潟大学)
「ドイツにおける国立大学法人化の新動向」 金子 勉 (京都大学) 「ドイツにおける教育領域への『新制御モデル』導入」 南部 初世 (名古屋大学) 「ドイツにおける学力問題と学力向上政策 --- 教育行政の社会的基盤 ---」 柳澤 良明 (香川大学) 「コロンブスは日独でどのように教育されるか --- 歴史認識空間の日独比較試論 ---」 増井 三夫 (上越教育大学) |
|---|
|
|
第23回 |
2004年5月24日
「クラウス・モレンハウアーの美的人間形成論をめぐって」 小川 史(早稲田大学大学院) 「ドイツにおける質的学校・青少年研究の動向と『生徒のライフストーリー研究』:ポストモダンにおける青少年の学校体験の解明に向けて」 ビアルケ千咲(国際基督教大学) |
|---|
|
|
第22回 |
2004年3月27日(土)
「学校のスポンサリング --- 論点紹介を中心として」 前原健二(東京電機大学)
「DDRの文化館からBRDの社会文化センターへの転換 --- その断絶性と連続性をめぐって --- 」 谷 和明(東京外国語大学)
|
|---|
|
|
第21回 |
2003年12月20日(土)
「ヘンティッヒとギーゼッケの脱学校論の相違 --- ドイツ教育学における解放的関心 --- 」 牛田伸一(日本大学)
「ドイツのキャリア教育とデュアルシステム」 坂野慎二(国立教育政策研究所)
|
|---|
|
|
第20回 |
2003年7月26日(土)(拡大フォーラム)
「戦間期オーストリアの学校改革 --- オットー・グレッケルのレーアプラン改革に焦点をあてて ---」 伊藤実歩子(京都大学大学院)
「日独の生涯学習政策の比較 --- 学習内容・学習者・財源の三つの視点から --- 」 安部耕作(近江八幡市教育委員会 「クラフキの『鍵的問題』構想とドイツの総合的学習」 高橋英児(山梨大学) 「ドイツにおける教員の人事評価」 柳澤良明(香川大学) 「ヴァイマル共和国における『ドイツ女性医師同盟』の社会的活動」 田村栄子(佐賀大学) 「ドイツと教授学研究と私」 的場正美(名古屋大学) |
|---|
|
|
第19回 |
2003年5月24日
「ドイツにおける大学評価の意義と課題」 井上朋美(早稲田大学研究生)
「ドイツの学校法制と学校法学」 結城忠(国立教育政策研究所)
|
|---|
|
|
第18回 |
2003年3月22日
「19世紀ドイツの古典語教育・古典研究と国民形成の係わりの理念的な背景」 曽田長人(群馬大学非常勤講師)
「現代ドイツの大学改革」 別府昭郎(明治大学)
|
|---|
|
|
第17回 |
2002年12月21日
「ドイツの教育におけるイスラーム --- 教師のスカーフ着用問題を中心に --- 」 斎藤一久(早稲田大学)
「 学校および学校外教育の利用に関する親の教育戦略 --- 日独比較の試み --- 」 ビアルケ千咲(東京大学)
|
|---|
|
|
第16回 |
2002年10月26日
「米占領下ドイツ(1945-1949)における教育改革の「失敗」と独立後の改革を実現させたもの:日本の事例との比較からの一考察」 柴田政子(同志社大学非常勤講師)
「学校プログラム」政策下の学校管理・運営の動態 --- ドイツ・ヘッセン州校長意識調査から」 前原健二(東京電機大学) |
|---|
|
|
第15回 |
2002年7月27日(拡大フォーラム)
「ドイツの通知表に関する一考察」 卜部 匡司 (広島大学大学院)
「ビーレフェルト実験学校の理念と展開」 原田 信之 (岐阜大学) 牛田 伸一 (創価大学大学院)
「旧東ドイツ地域におけるカリキュラム変革 --- 大学教員の移動に 焦点をあてて --- 」 大野 亜由未 (日本学術振興会特別 研究員) 「社会文化運動とボイス(J.Beuys) の『社会的芸術』論 --- ハンブルク市 Parrk Fiction の事例に即して --- 」 谷和明(東京 外国語大学) |
|---|
|
|
第14回 |
2002年5月25日
「大衆化に伴うドイツの高等教育政策の変遷 --- 大綱法成立以後を中心に --- 」 井上朋美 (早稲田大学大学院) 「継続教育から生涯学習へ --- 概念の変遷をめぐる学習論的考察 --- 」 三輪建二 (お茶の水女子大学)
|
|---|
|
|
第13回 |
2002年3月30日
「現代ドイツ学校会議に関する研究 --- ベルリンの現行法および改正法案の比較分析を通して --- 」吉川 永 (埼玉県鳩ヶ谷高等学校)
「ドイツにおける学校と企業のパートナーシップ」 坂野 慎二 (国立教育研究所) |
|---|
|
|
第12回 |
2001年12月8日
「戦後ドイツのマイノリティーに対する歴史的流れ --- 外国人労働者、帰還者、難民それぞれの問題 --- 」 帆足 哲哉(国士舘大学大学院)
「ヨーロッパにおける少年法制と少年犯罪」「ドイツの教科書法制」 結城 忠(国立教育研究所)
|
|---|
|
|
第11回 |
2001年10月27日
「現代ドイツにおける『価値教育』教科に関する一考察 --- 宗教科代替科目の導入と展開を中心に --- 」 濱谷 佳奈 (上智大学大学院)
「理性の公的使用と私的使用 --- カントの説をてがかりに --- 」 別府 昭郎 (明治大学)
|
|---|
|
|
第10回 |
2001年7月21日(拡大フォーラム)
「リット教育思想における『指導』と『放任』の問題」 庄司 倫子(お茶の水女子大学大学院)
「カント教育学講義の歴史的考察」 藤井 基貴(名古屋大学大学院)
「ドイツ民法典における親の懲戒権の変容過程」 荒川 麻里(筑波大学大学院) 「犠牲者神話と二つの真実 --- オーストリア共和国の自国史像 --- 」 近藤 孝弘(名古屋大学) 「現代ドイツにおける『良い学校』に関する理論構築と学校の自律性の拡大」 遠藤 孝夫(弘前大学) |
|---|
|
|
第9回 |
2001年5月26日
「ドイツにおける学校の自律化と教育の機会均等」 前原 健二(東京電機大学)
「現代ドイツにおける道徳教育事情」 福田 弘(筑波大学)
|
|---|
|
|
第8回 |
2001年3月24日
「19世紀末のドイツ中等学校改革論争」 溝道 修史(明治大学大学院)
「ドイツ社会文化運動の新局面 --- 運動と経営の相克をめぐって --- 」 谷 和明(東京外国語大学)
|
|---|
|
|
第7回 |
2000年12月9日 (拡大フォーラム)
「大学生からみたギムナジウムの教育課程」 坂野慎二(国立教育研究所)
「国民読本の構想 --- ゲーテとニートハンマー」 井戸田総一郎(明治大学)
「生涯学習関係職員の研修に関する日独比較研究」 「日本の生涯学習関係職員の研修のあり方」 倉持伸江(お茶の水女子大学大学院) 「ドイツの継続教育関係職員の養成と研修」 三輪建二(お茶の水女子大学) |
|---|
|
|
第6回 |
2000年10月28日
「大学とその周辺社会 --- 中世ハイデルベルクの都市と大学 --- 」 寺岡 英裕(中央大学大学院)
「近代教育と新教育運動 --- ドイツ田園教育舎を事例とした一解釈 --- 」 山名 淳(東京学芸大学)
|
|---|
|
|
第5回 |
2000年7月22日
「日独中学生の生活構造と親の学校観」 ビアルケ 千咲(東京大学大学院)
「旧東ドイツの地方都市における教育行政」 佐藤義雄(国士舘大学)
|
|---|
|
|
第4回 |
2000年6月3日
「ドイツの大学教育における構造・諸問題・改革動向」 Dr. von Queis (ハンブルク防衛大学上級研究員・明治大学客員教授)
|
|---|
|
|
第3回 |
2000年3月25日
「ドイツの学校参加に関する研究」 吉川 永(上越教育大学大学院)
「オーストリアにおける過去の抑圧と克服」 近藤孝弘(名古屋大学)
|
|---|
|
|
第2回 |
1999年12月11日
「ワイマール期の父母協議会・断章」 前原健二(東京電機大学)
「中等教育段階1の統合化」 坂野慎二(国立教育研究所)
|
|---|
|
|
第1回 |
1999年10月16日
「フリードリヒ・アウグスト・ヴォルフの『古代学の叙述』 --- 19世紀ドイツにおける古典語教育・古典研究のプログラム」 曽田長人(東京大学大学院)
「国旗・国歌法制の比較法学 --- 日本・ドイツ・アメリカ --- 」 結城忠(国立教育研究所)
|
|---|